-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
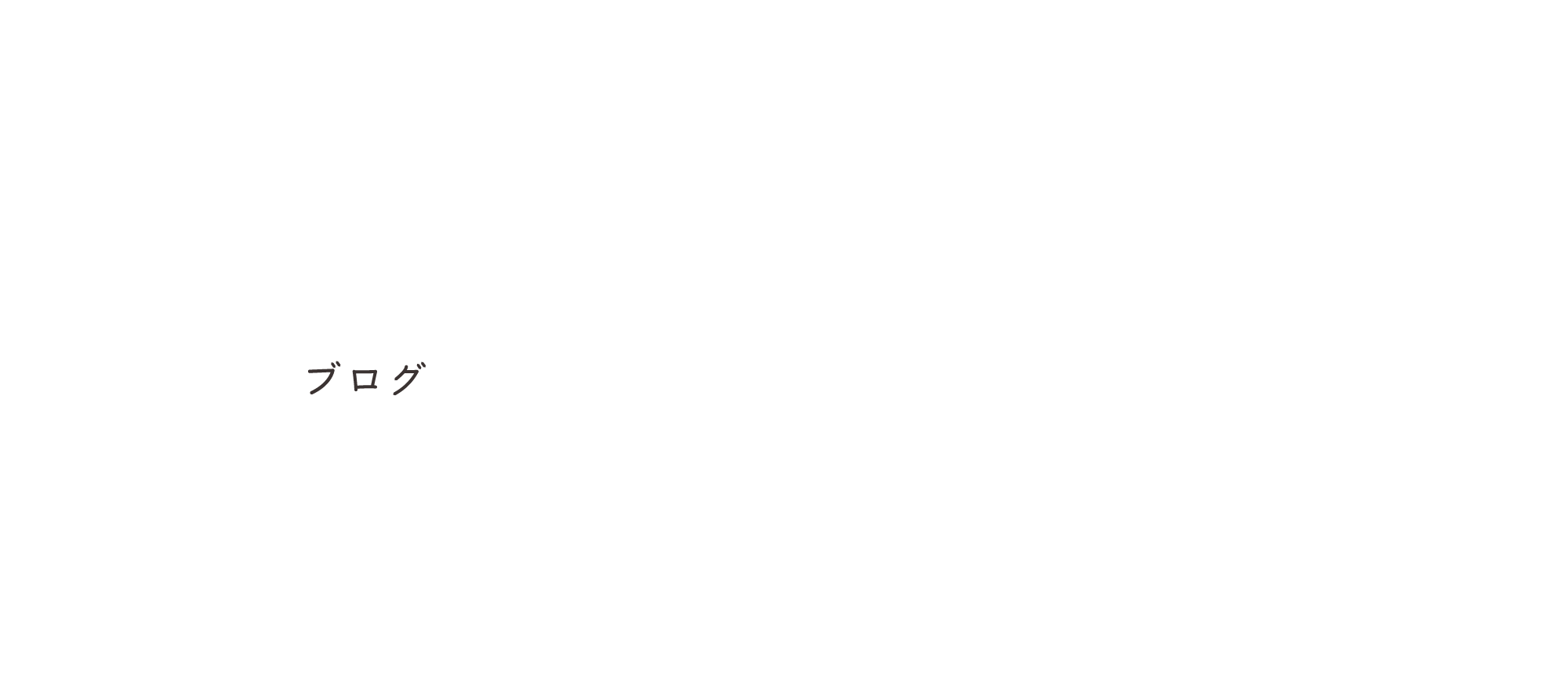
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
さて今回は
服薬支援とヒヤリ・ハット対策:間違えない仕組みと“飲める”工夫 💊
在宅の服薬は“人の善意と記憶”に頼ると崩れます。
仕組み化(一包化・ピルケース・アラーム・置き場所)と、飲みやすさのデザイン(姿勢・剤形・水分・声かけ)で、誤薬・飲み忘れ・飲み過ぎを防ぎます。薬剤師との連携、ヒヤリ・ハットの共有方法まで、現場でそのまま使える型を共有します。🧩
1|訪問介護で起きやすいリスク5つ
1) 飲み忘れ/重複内服:家族とヘルパーが二重投与。🕑
2) タイミングミス:食前・就寝前のずれ。
3) 誤薬:隣家の薬袋・旧薬の混在。
4) 飲みにくさ:大きい錠剤、苦味、嚥下機能低下。
5) 副作用見逃し:ふらつき・眠気・便秘・低血圧など。
2|“間違えない仕組み”を先に作る(5点セット)
• 一包化+氏名・時間の大ラベル:薬局に依頼し、袋の表に氏名・服用時刻を大きく明記。👤
• ピルケースは“1列1日”:朝・昼・夕・寝る前の4マス。使った列は空にして視覚で確認。
• 服薬カレンダー:カレンダーに○×をつけ、写真で共有(家族・ケアマネ・薬剤師)。
• アラーム:時計/スマホ/見守り端末で時刻を固定化。
• 置き場所の固定:食卓の同じ角。冷蔵庫や寝室に分散させない。📍
3|服薬介助フロー(言い回しの例つき)
1) 準備:手指衛生→薬と水分→氏名・時刻・薬名を確認。
2) 予告:「○○さん、朝のお薬を一緒に確認して、飲みましょうね」😊
3) 確認:ラベル読み上げ→本人にも読んでもらう/指差し確認。
4) 姿勢:座位で軽い前傾、足底接地。嚥下が不安定なら頸部前屈。
5) 内服:一口ごとに嚥下を待つ。追い飲み・まとめ飲みは避ける。
6) 観察:むせ・表情・めまい・眠気。
7) 記録・保管:○×を記録→未使用薬は元の場所に戻さない(誤薬防止)。📝
4|“飲めない”を“飲める”へ:剤形と小ワザ
• 大きい錠剤→口腔保湿→水先→少量ずつ。砕く/割るは自己判断NG(薬剤師へ相談)。
• 粉薬の苦味→ゼリーやプリンと“別口”で(混ぜ込みは薬剤師指示がある時のみ)。
• 嚥下不安→少量・ゆっくり+とろみ飲料の活用(使用法はパッケージ指示に沿う)。
• 利尿薬→午前中に(夜間頻尿を避ける運用)。
5|薬剤師との連携ポイント 🤝
• 残薬・飲み忘れを写真で共有→調整(回数・時刻・剤形)。
• 副作用サイン(ふらつき・便秘・眠気・血圧低下)を時系列で伝える。
• お薬手帳は常に最新に。訪問看護・主治医の情報提供書で三者連携。
6|ヒヤリ・ハットは“仕組みに反映”がゴール
• テンプレ記録:〈日時〉〈状況〉〈起因〉〈対応〉〈再発防止〉を3行で。
• ダブルチェック:訪問前後にラベル読み上げの習慣化。
• 旧薬廃棄:本人・家族と合意し、保管箱を分ける。🗃️
7|現場ケース
• 睡眠薬でふらつくFさん:就寝前→夕食後へ時刻変更+半量へ(医師調整)。夜間転倒が消失。
• 抗生薬飲み忘れのGさん:アラーム+服薬カレンダー写真共有で完遂率↑。
8|今日から使えるチェックリスト ✅
☐ 一包化・ラベル・置き場所は固定化したか。
☐ 服薬介助フロー(準備→確認→姿勢→内服→観察→記録)を守ったか。
☐ 副作用サインを観察・共有したか。
☐ ヒヤリ・ハットを3行で記録し、仕組みを変えたか。
9|まとめ
服薬支援は“正しい手順×見える化”。人に頼らず仕組みに頼ることで、在宅でも安全と継続が両立します。🌟
![]()