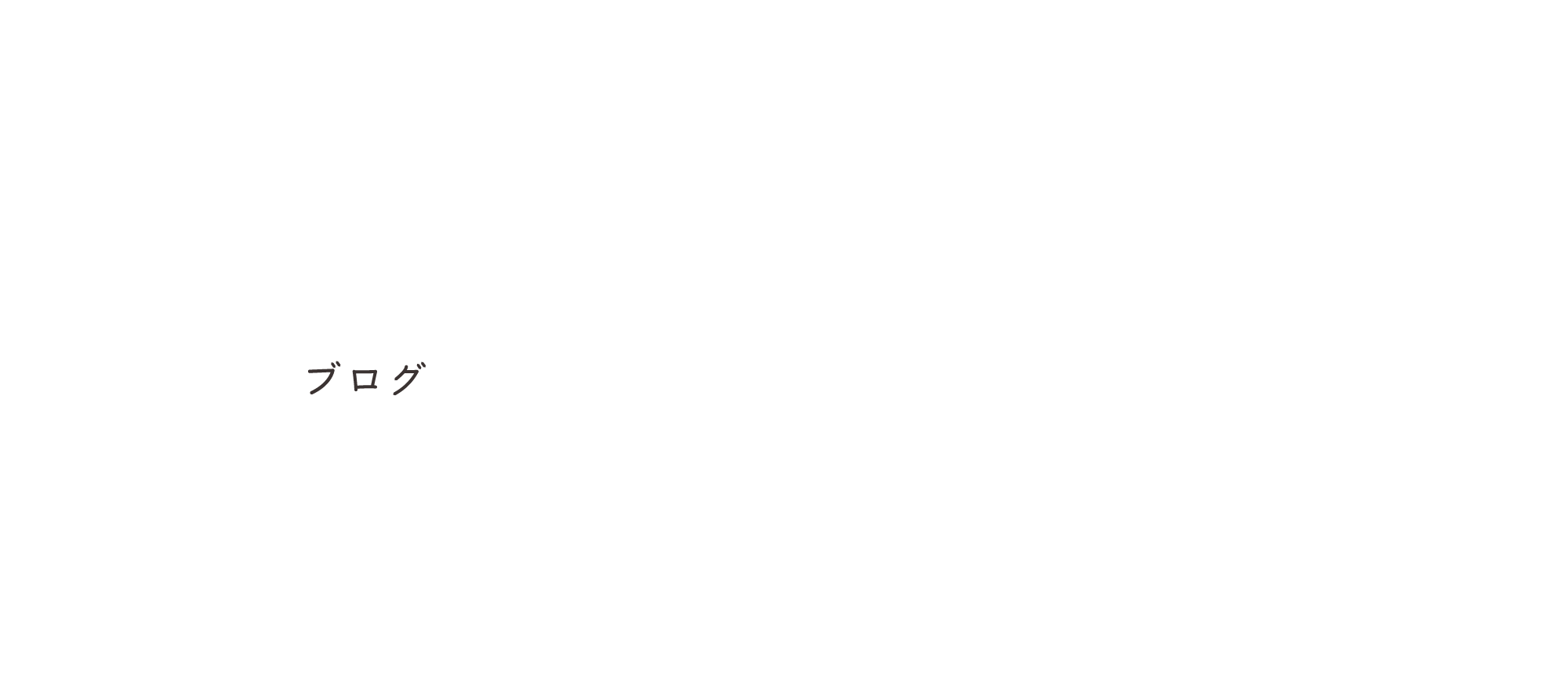
カテゴリー別アーカイブ: 日記
やまもものよもやま話~「人と人の仕事」~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
~「人と人の仕事」~
訪問介護の現場で、最も大切なのは何でしょうか。技術?経験?スピード?
もちろんどれも大事です。でも、訪問介護の魅力の中心にあるのは、人と人の関わりです。✨
同じ支援内容でも、声のかけ方一つで利用者さまの安心感は大きく変わります。訪問介護は、コミュニケーションの力が“ケアの質”を底上げする仕事なのです。
1)「安心」をつくるのは、技術+言葉の温度
たとえば、入浴介助や排泄介助など、利用者さまにとって緊張や羞恥心が伴う場面があります。
その時、ヘルパーが無言で作業のように進めてしまうと、不安が増えることがあります。
逆に、丁寧な説明と優しい声かけがあると、利用者さまは安心して身を任せやすくなります。
-
「今から体を支えますね」
-
「ゆっくりいきましょう」
-
「寒くないですか?」
-
「大丈夫、焦らなくていいですよ」
こうした一言が、ケアを“安全”にするだけでなく、“尊重”の時間に変えていきます。✨
2)距離が近いからこそ「境界線」も大切
訪問介護は自宅に入る仕事。生活のプライベート領域に入るからこそ、適切な距離感が重要です。
親しさは大切。でも馴れ馴れしすぎない。遠すぎず、近すぎず。
この“ちょうどいい距離感”をつくれることは、訪問介護の専門性の一つです。✨
利用者さまが安心する距離感は人それぞれ。
-
話を聞いてほしい人
-
静かに見守ってほしい人
-
作業を優先してほしい人
その日の体調や気分でも変わります。
だからヘルパーは、表情や声のトーン、反応を見ながら調整します。これは機械にはできない、人の仕事です。
3)“孤独”に寄り添える仕事️
在宅で暮らす方の中には、家族が遠方だったり、近所付き合いが減っていたりして、日中ほとんど誰とも話さない方もいます。
訪問介護の時間が、その方にとって貴重な“人と話せる時間”になることがあります。
雑談は、ただの世間話ではありません。心の健康を支える大切な時間です。
「今日は寒いですね」
「この前のテレビ、見ました?」
「昔はどんなお仕事されてたんですか?」
そんな会話が、利用者さまの表情を明るくし、生活への意欲につながることもあります。✨
4)ヘルパーの存在が「地域の見守り」になる️
訪問介護は、地域の中で利用者さまを見守る役割も担っています。
日々訪問するからこそ、ちょっとした変化に気づきやすい。
たとえば
-
いつもより元気がない
-
食欲が落ちている
-
部屋の様子がいつもと違う
-
転倒リスクが増えている
こうした気づきを共有することで、必要な支援につながる可能性があります。✨
訪問介護は、地域の安心を支える大切なインフラでもあるのです。
訪問介護は、言葉と気配りでケアの価値が上がる仕事
訪問介護の魅力は、技術だけでなく、人としてのあたたかさがそのまま仕事の価値になること。
会話、気配り、距離感、見守り…。
人と人が向き合うからこそ生まれるケアの力が、訪問介護にはあります。
![]()
やまもものよもやま話~「小さな変化が、大きな希望になる」~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
~「小さな変化が、大きな希望になる」~
訪問介護の現場では、目に見えるドラマが毎日起こります。大きな出来事ではなくても、日常の中にある小さな変化が、本人にとっては大きな希望になることがあります。🌈
訪問介護の魅力は、そうした“変化の芽”を見つけ、そっと支えて育てていけることです。🌱😊
1)「できること」を奪わない支援が、本人を強くする💪
介護の現場でよくあるジレンマが、「手伝えば早いけど、手伝いすぎると力が落ちる」という問題です。
訪問介護では、一対一だからこそ、利用者さまの“できる部分”を丁寧に見極められます。
-
立ち上がりは手すりがあればできる
-
食事は刻みや一口介助で自分で食べられる
-
更衣は片腕だけ手伝えば自分でできる
こうした“できる”を残す支援は、生活機能だけでなく、心の自信にもつながります。✨
「自分でできた」が増えると、表情が明るくなる。
「今日もやってみよう」と意欲が出る。
その変化を一番近くで見られるのが、訪問介護の醍醐味です。😊🌼
2)生活リズムを整えることで、毎日が変わる⏰🌞
訪問介護は、生活の土台を整える役割も担います。
朝起きて顔を洗う、服を着替える、朝ごはんを食べる、部屋の空気を入れ替える。
当たり前のことが、体調や気分の変化で難しくなることがあります。
そんな時、ヘルパーが関わることで
-
朝の支度ができて一日が始まる🌞
-
食事が取れて体力が保てる🍚
-
部屋が整い気持ちが軽くなる🧺
-
会話が増えて孤独感が減る💬
こうした良い循環が生まれます。🔁✨
生活は“積み木”のようなもの。小さな土台が崩れると一気に不安定になります。訪問介護は、その土台を整えるプロの仕事です。
3)家族の負担を減らし、関係を守る👨👩👧👦💗
訪問介護は、利用者さまだけでなく家族にとっても大きな支えになります。
介護は愛情だけでは続けられない現実があります。仕事、子育て、遠距離、体力、精神的負担…。介護が家庭に入ることで、家族の関係がギスギスしてしまうこともあります。😢
そこで訪問介護が入ると、家族が「家族に戻れる時間」が生まれます。
介護者としての役割が少し軽くなることで、
-
優しく話せるようになる
-
一緒に食卓を囲める
-
無理をしないで済む
そんな変化が起こります。😊💗
訪問介護は、利用者さまの暮らしだけでなく、家族の暮らしも守る仕事です。
4)“専門職としての成長”が実感できる📚✨
訪問介護は、現場ごとに状況が違います。家の間取り、生活習慣、本人の希望、身体状況、家族構成、地域の支援体制…。同じ支援は一つとしてありません。
だからこそ、経験がそのまま力になります。🧠💪
-
どうすれば安全に移乗できるか
-
どうすれば本人の意欲を引き出せるか
-
どうすれば暮らしの中のリスクを減らせるか
こうした“考える介護”を積み重ねるほど、支援の質が上がり、信頼も増えます。📈✨
訪問介護は、技術だけでなく、観察力・コミュニケーション・判断力が磨かれる成長型の仕事です。
訪問介護は、小さな希望を積み上げる仕事🌱✨
訪問介護は、毎日の小さな“できた”を支え、生活のリズムを整え、家族の負担を軽くし、本人の尊厳を守る仕事です。
大きなことをしなくても、人の人生は変わります。
その変化の瞬間に立ち会えるのが、訪問介護の魅力です。😊🌼
![]()
やまもものよもやま話~その人の家で、その人らしさを守る~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
~その人の家で、その人らしさを守る~
訪問介護(ホームヘルプ)という言葉を聞くと、「食事や掃除の手伝いをする仕事」「高齢者の介護をする仕事」というイメージが先に立つかもしれません。もちろんそれも大切な役割です。でも、訪問介護の本質はそこだけではありません。
訪問介護とは、**“その人が、その人の家で、その人らしく暮らし続ける”**ための支援です。✨
施設と違い、訪問介護は利用者さまの生活の舞台に入らせていただく仕事。生活の歴史が詰まった空間で、日々の営みを支えるからこそ、そこで生まれる喜びややりがいはとても大きいのです。
1)「自宅で暮らし続けたい」という願いを叶える仕事️
多くの方が、年齢を重ねたり体が不自由になったりしても「できるなら自宅で暮らしたい」と願います。住み慣れた家、いつもの寝具、いつもの窓から見える景色、近所の人との挨拶、好きな音、好きな匂い…。それらは“生活の安心”そのものです。
訪問介護は、その安心を守る仕事です。介助の技術だけでなく、生活の流れを乱さず、本人のペースに合わせ、できることを奪わない支援が求められます。
たとえば、着替え一つとっても「全部やってあげれば早い」だけではなく、
-
ボタンは自分で留めたい
-
好きな服を自分で選びたい
-
今日はゆっくりしたい
そうした気持ちを尊重しながら、必要なところに手を差し伸べる。✨
“支える”とは、相手の尊厳を守ること。訪問介護はそれを毎日の現場で実践できる仕事です。
2)生活援助も身体介護も「暮らしの質」を上げる力がある
訪問介護には、生活援助(掃除・洗濯・調理など)や身体介護(排泄・入浴・移乗・食事介助など)があります。どちらも、ただ“作業”をこなす仕事ではありません。
たとえば調理。単に栄養を満たすだけでなく、
「今日はこの味が食べたい」「昔よく作った煮物が好き」など、食の記憶や楽しみを支える役割があります。
掃除や洗濯も同じで、清潔な環境は健康面だけでなく、気持ちの明るさに直結します。部屋が整うと、心まで整う。
身体介護では、ほんの少しの手添えで「自分で立てた」「自分で食べられた」という成功体験につながることもあります。
その小さな“できた!”が積み重なるほど、自信や意欲が戻ってくる。✨
訪問介護は、生活の細部から利用者さまの“生きる力”を支えているのです。
3)一対一だからこそ、信頼関係が深い
訪問介護の大きな魅力は、基本的に一対一の関わりであること。施設のように多人数のケアを同時に行う場面より、目の前の利用者さまに集中できる時間が長いのが特徴です。✨
その分、利用者さまの変化にも気づきやすい。「今日は声の張りが少ない」「いつもより眠そう」「表情が硬い」など、ささいな変化に気づくことで、早めの声かけや関係者への共有につながります。
そして何より、信頼関係が築けたときの喜びは格別です。
最初は警戒していた方が、少しずつ笑ってくれるようになったり、
「あなたが来ると安心する」
そんな言葉をいただけた瞬間、胸が熱くなります。
訪問介護は、心の距離が近づくほど、仕事の意味が深まっていく仕事です。
4)「その人の人生」に触れられる尊さ
訪問介護では、利用者さまの生活空間に入るからこそ、人生の物語に触れる機会があります。写真、趣味の道具、仏壇、家族の思い出、昔の仕事の話…。
介護は身体の支援だけではなく、人生への敬意が土台にある仕事。✨
「昔はこうだったんだよ」「この家を建てたときはね」
そんな話を聞く時間は、利用者さまにとっても“自分の歴史を認めてもらえる時間”になります。
訪問介護は、暮らしと尊厳を支える仕事✨
訪問介護の魅力は、日常の中で、その人の“当たり前”を守り続けること。
派手さはないかもしれません。でも、生活の質を上げ、安心をつくり、自立を支え、人生に寄り添う。
誰かの暮らしの土台を支える、誇りある仕事です。
![]()
やまもものよもやま話~119・嘔吐・低血糖・熱中症の初動フロー 🚑~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
119・嘔吐・低血糖・熱中症の初動フロー 🚑
“焦らず、速く、同じ型で”。緊急時は安全確保→観察→連絡→記録の順で動きます。発作・窒息・転倒・発熱・嘔吐・低血糖・熱中症の現場プロトコルを、在宅仕様で整理しました。📟
1|共通初動(30秒でやること)
1) 安全確保:転倒物・火・水をどける。窓を開け換気。
2) 呼吸と意識:呼びかけ・胸の上下・皮膚色。
3) 体位:呼吸苦→上体挙上、嘔吐→回復体位(横向き)。
4) 連絡:状況により119/訪問看護/主治医。同居家族にも短く共有。
5) 記録:時刻・症状・対応・結果を3行で。📝
2|症状別プロトコル
• 窒息(むせ・青ざめ・声が出ない)
o 咳を促す→出なければ背部叩打。意識低下や呼吸停止の疑い→119。
o 食後30分は座位維持。“追い飲み”禁止。
• 嘔吐・誤嚥疑い
o すぐ回復体位、口腔をやさしく清拭。口腔乾燥ケア。
o 発熱・咳が出たら看護→医師へ連絡。
• 低血糖(冷汗・手指の震え・ふらつき)
o 意識明瞭:ブドウ糖10〜20g(ゼリー等)→15分後再評価。
o 意識障害:119、口に入れない、保温。
• 熱中症(めまい・気分不良・発熱)
o 冷却(首・腋・鼠径)、涼しい部屋へ。水分・電解質を少量ずつ。
o 意識障害・けいれん・高体温→119。
• 転倒
o 頭部打撲/抗凝固服用/いつもと違う様子→119/看護。
o その場で無理に起こさず、痛み部位を確認→必要ならシートで移動。
• 発熱
o 38℃以上+呼吸苦/強い咳/ぐったり→看護→主治医。保温と水分。😷
3|“呼ぶ順番”の決め方(壁に貼る)
• 命の危険が疑われる:119→訪看→家族。
• 評価と処置が必要:訪看→主治医。
• 生活調整で収まる:ケアマネへ共有。
4|緊急セット(玄関近くに常備)
• 連絡台紙(連絡先と優先順位)
• 体温計・パルスオキシメータ
• ブドウ糖ゼリー/経口補水液
• 清拭用具・手袋・袋
• 懐中電灯・足元灯🔦
5|現場ケース:深夜の嘔吐で慌てたQさん
• 初動:回復体位→口腔清拭→上体挙上。体温37.8℃、SpO₂ 95%。
• 連絡:訪看へ。翌朝に看護訪問、主治医判断で経過観察。
• 結果:肺炎化せず回復。家族と“回復体位ポスター”を作成。🌙
6|今日から使えるチェックリスト ✅
☐ 共通初動(安全→観察→連絡→記録)を実践したか。
☐ 回復体位・上体挙上をチームで統一したか。
☐ 呼ぶ順番の台紙を掲示したか。
☐ 緊急セットを玄関近くに集約したか。
7|まとめ
緊急時は“いつも通りの型”が命を守る。貼る・置く・決めるで、迷いをなくしましょう。🚑
![]()
やまもものよもやま話~訪問看護・主治医・薬剤師と賢くつながる 🏥~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
訪問看護・主治医・薬剤師と賢くつながる 🏥
在宅ケアの“推進力”は連携にあります。何を・いつ・どう伝えるかを仕組みにして、主治医・訪問看護・薬剤師・リハ職と迷いなく連動できる体制を作りましょう。現場で使えるSBARテンプレ、連携の優先順位、会議の回し方、プライバシー配慮までまとめます。🤝
1|連絡の原則はSBAR(そのまま使える型)
• S:状況(今起きていること):「本日16:00、38.2℃の発熱、咳増加」
• B:背景(既往・最近の変化):「昨日から食事量半分、先週尿路感染で抗生薬終了」
• A:評価(考えられること):「感染再燃の可能性、脱水も疑い」
• R:要請(してほしいこと):「受診要否の判断、看護訪問の追加可否」📞 → 音声→簡潔な書面(メモ/メール/FAX)の順で残すと、チームで追跡しやすい。
2|“誰に何を”の分担表(迷わないための地図)
• 主治医:診断・処方・方針決定。発熱・意識変容・急な痛みはまず相談。
• 訪問看護:バイタル評価・症状緩和・吸引・褥瘡ケア。緊急の初動は看護へ。
• 薬剤師:残薬・相互作用・剤形変更・アドヒアランス。
• リハ職(PT/OT/ST):活動量・嚥下・住環境。“できる”を増やす処方箋。
• ケアマネ:サービス調整・記録のハブ。会議設定・合意形成。🗺️
3|“時間”で考える連携フロー
• 即時(0〜1時間):119/訪看/主治医連絡(発作・窒息・重度の呼吸困難)。
• 当日(数時間以内):発熱・急な疼痛・脱水疑い→看護追加訪問、主治医相談。
• 近日(1〜3日):食欲低下・睡眠悪化・BPSD変動→看護/薬剤師/リハと調整。
4|定期連携:ミニカンファの回し方(30分版)
1) ゴール再確認:「生活目標=“来客を迎えたい”」
2) データ共有:体重・食事量・歩行・口腔・排泄・睡眠の推移を1枚で。
3) 課題の優先度:重大性×頻度でTop3。
4) 次の一手:担当・期限・評価指標を決める。🧭
5|連携を強くする“見える化”ツール
• 共同ノート:写真付き・週1で要点を記録(紙/アプリどちらでも)。
• 服薬カレンダー写真:飲み忘れの把握と調整に効果大。
• 食事ギャラリー:栄養士提案のベースに。📸
6|プライバシーと同意(守るべきライン)
• 目的と範囲を本人・家族に説明し、同意を得てから共有。
• 最低限の情報を必要な相手に。鍵・紙の持ち出しはルール化。🔐
7|現場ケース:発熱時の迅速連携
• 状況:37.9→38.3℃、食欲低下、咳あり。
• 初動:看護に連絡→バイタル評価と口腔・水分調整→主治医判断で抗生薬再開。
• 結果:在宅のまま3日で解熱。写真と記録で再発時も同手順で対応。🌟
8|今日から使えるチェックリスト ✅
☐ SBARで連絡したか(音声→書面)。
☐ 連絡先と優先順位(119/看護/主治医)を台紙に掲示したか。
☐ 週1の“共同ノート”で見える化したか。
☐ 同意とプライバシー保護を徹底したか。
9|まとめ
連携は“偶然”ではなく“設計”。型と地図があれば、誰が担当でも同じ品質で支えられます。🏥🤝
![]()
やまもものよもやま話~最期まで“いつもの暮らし”を ~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
最期まで“いつもの暮らし”を
在宅での看取りは、“医療の現場”ではなく“暮らしの延長”。症状緩和(痛み・息苦しさ・せん妄・むくみ)、家族の不安への寄り添い、連絡網と役割分担を整えることで、穏やかな時間が流れます。宗教・文化・価値観への配慮も忘れずに。️
1|“その人らしさ”の確認から始める
• 何を大切にしたいか:音楽、光、香り、写真、衣類、誰と過ごすか。
• どこで過ごすか:居間?寝室?窓際?ベッドの向きまで希望を聞く。
• 食と水:無理に食べさせない。“口を潤す”が中心に。
2|症状緩和の土台(非薬物的アプローチ)
• 痛み:体位変換、クッション・枕の配置、温罨法。触れる強さは痛みの前後で変える。
• 呼吸困難:上半身を30〜45°挙上、扇風機やうちわで頬に風を当てる。口すぼめ呼吸のガイド。️
• せん妄:照明と時計、家族の声、落ち着く音楽。刺激は“少しだけ”。
• むくみ:心臓よりやや高く足を上げる。肌の保湿と優しいマッサージ。
3|口腔ケアとスキンケア(最期のやさしさ)
• 口:保湿ジェル・スポンジで口内を湿らせる。唇には薄くワセリン。
• 皮膚:摩擦を避け、シーツの皺を正す。保湿クリームで触れるケアを。
• 排泄:おむつは羞恥に配慮しつつ、清潔・乾燥を保つ。
4|家族の不安に寄り添う言葉
「眠る時間が長くなるのは、体の自然な変化です。水分は口を潤すことを大切にしましょう。呼吸が変わる時は、上体を少し起こして、頬に風を当てます。心配な時はいつでも電話してください。」
5|連絡網と“緊急ではないけど不安”の受け皿
• 窓口:訪問看護・主治医・ケアマネの時間外の連絡手順を紙で掲示。
• 合図:呼吸が荒い/痛みが強い/意識が変わる→まず訪問看護。
• 最期のとき:死亡診断の流れ、宗教者の連絡、葬儀社の段取りを事前に共有。
6|宗教・文化・家族の儀礼
• 祈り・読経・音楽などの希望を確認。写真や思い出の品の配置。
• 触れ方・見送り方:地域や宗教の作法に合わせる。️
7|現場ケース:窓辺で眠りたいPさん
• 希望:朝日が差す窓辺で最期の時間を過ごしたい。
• 環境:ベッドを窓際へ移動、上体30°挙上、好きな音楽を小さく。
• 家族:役割分担(口腔保湿・足の保湿・連絡係)。
• 結果:呼吸のしやすさが増し、家族との会話が穏やかに続いた。️
8|今日から使えるチェックリスト ✅
☐ 本人の大切にしたいもの・過ごし方を確認したか。
☐ 症状緩和の非薬物的ケアを実施したか。
☐ 口腔・皮膚ケアを“やさしく”続けたか。
☐ 連絡網と時間外の手順を掲示したか。
9|まとめ
看取りは“何もしない”時間ではなく、やさしさを重ねる時間。いつもの暮らしを少しだけ整え、最期までその人らしさを守りましょう。
![]()
やまもものよもやま話~孤立・虐待・緊急のサインを見逃さない 👀~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
孤立・虐待・緊急のサインを見逃さない 👀
独居は“気づけば悪化”が最大のリスク。郵便物・冷蔵庫・服装・近隣情報という“生活センサー”と、安否確認・センサー・地域連携の三層で見守ります。虐待や経済搾取の兆候、緊急連絡の優先順位も整理。🧭
1|日常の観察ポイント(生活センサー)
• 郵便物:未開封が増える、督促状の有無。
• 冷蔵庫:期限切れ・同じ食材の過剰、飲料・たんぱく源の不足。
• 服装:季節と不一致、同じ服の長期連続、汚れの放置。
• 家の音と匂い:テレビつけっぱなし、異臭・腐敗臭。
• 近隣の声:夜間の大声・ドアの開閉が減った等。👂
2|生活課題と支援の組み立て
• 食:配食・ドラッグストア配送・冷凍弁当のストック化。
• 買物:定期配送+置き配、プリペイド決済で金銭トラブル予防。
• 掃除:2畳ルールと道具の定位置化。転倒しやすい床を優先。
• 通院:訪問診療・服薬カレンダー・オンライン面談の導入。
3|安否確認の設計(毎日運用できる仕組み)
• “朝の合図”:冷蔵庫の見守り電源/ポットの使用検知/ドアの開閉センサー。
• “昼の合図”:配食の受け取り記録、お弁当写真の共有。
• “夕の合図”:テレビの見守り赤外線や照明の点灯確認。📡
• 連絡網:近隣キーパーソンを2名設定(鍵は管理しないが、通報役として)。
4|虐待・経済搾取の兆候(迷ったら記録→相談)🚨
• 身体:不自然なあざ、体重減少、清潔不良。
• 心理:過度の怯え、特定人物の話題で沈黙。
• 経済:口座の急減、不自然な契約、高額現金の持ち歩き。
• 対応:事実の記録→ケアマネ・地域包括へ相談。緊急は110/119。📞
5|現場ケース:新聞が山のOさん
• 観察:郵便受けに1週間分の新聞。冷蔵庫は飲料のみ。
• 仮説:無気力と食の低下。日中活動の減少。
• 介入:配食+昼の電話合図、週2デイで活動量を回復。
• 結果:夕の不穏が減り、体重が1.2kg回復。🌟
6|今日から使えるチェックリスト ✅
☐ 郵便・冷蔵庫・服装・匂いの4点を観察したか。
☐ 朝昼夕の合図を設計したか。
☐ 虐待・経済搾取の兆候を事実で記録したか。
☐ 連絡網(近隣2名+公的窓口)を整えたか。
7|まとめ
独居見守りは“人×テクノロジー×地域”の三層で安心をつくる。続けられる仕組みが命です。🏠
![]()
やまもものよもやま話~ 家族支援~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
さて今回は
罪悪感・疲労・葛藤に寄り添う
① 家族の感情曲線を知る(名前をつけるだけで楽になる)
-
感情の流れ:
否認 → 怒り → 取引 → 抑うつ → 受容
日によって行き来するのが自然な反応。 -
言葉がけのポイント
「そう感じるのは自然です」
「一緒に作戦を立てましょう」 -
比較の罠
「隣の家はできている」→ 家庭ごとに条件・支援体制が違うと説明する。
② 期待値の再設計:家族会議の“型”
1️⃣ 目的共有:「“できることを増やす”を優先に」
2️⃣ 役割分担:家事・見守り・通院同行を具体的に割り振る
3️⃣ レスパイト計画:デイ・ショート・訪問看護など、使い時を決めておく
4️⃣ 連絡網の整備:昼/夜/緊急時の窓口を一本化
“話し合い=負担調整の時間”と位置づけることで、家族の安心感が増す。
③ よくある葛藤と介入
| 家族の葛藤 | 対応・提案 |
|---|---|
| 「入浴は毎日!」論争 | 安全と体力を優先し、部分清拭+足浴を提案。 |
| 「自分がやるのが愛情」 | “やり方を整える=愛情”と再定義。用具・導線を省力化。 |
| 金銭不安 | 小額財布+レシート貼付で見える化。詐欺対策も併せて説明。 |
④ 家族への説明トーク例
「“毎日完璧”より、“無理なく続くやり方”が安全です。
今日は足湯と清拭で温まって、明日入浴にしましょう。
記録を写真で共有して、うまくいった型を増やしますね。」
言葉+共有+振り返りで“成功体験”を可視化。
⑤ レスパイトの導入は“後ろめたさ”に効く
-
事実:休む家族ほど介護を長く続けられる。
-
選択肢:
・デイの短時間利用
・入浴のみ利用
・ショートステイ“半日”から始める -
休むサイン:
怒りっぽい/眠れない/涙が出る → 「そろそろ休む合図」️
“休む=続けるための技術”として伝える。
⑥ 境界線とセーフティ(ヘルパーを守る)️
-
金銭・鍵・通帳:
原則として触れない。受け渡しは第三者立ち会い。 -
ハラスメント対応:
複数訪問・記録・通報フローを事前に説明。 -
個人連絡先:
利用者・家族に渡さず、事業所を窓口に統一。
⚠️ 現場を守る仕組みが「継続支援」の土台になる。
⑦ 現場ケース
介護疲れで口論が続いていたNさん一家
-
状況:入浴頻度をめぐり夫婦喧嘩が常態化。
-
介入:家族会議で週2全身浴+隔日清拭に合意。
→ 「できた日シール」で成功体験を可視化。 -
結果:口論が半減し、会話時間が増加。
「達成感の共有」が家族の雰囲気を変える。
⑧ 今日から使えるチェックリスト ✅
☐ 家族の感情に“名前”をつけて返したか
☐ 役割・連絡網・レスパイトの3点セットを提案したか
☐ 金銭・鍵・通帳には触れない運用にしたか
☐ ハラスメント対応の窓口を周知したか
⑨ まとめ
家族支援は「説得」ではなく「整えること」。
言葉 × 選択肢 × 休む仕組み を整えることで、
家族はもう一度“介護を続ける力”を取り戻します。
寄り添いとは、我慢を減らし、希望を見える形にすること。
![]()
やまもものよもやま話~✍️ 記録の質でケアは変わる~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
さて今回は
SOAP・経過記録・引き継ぎの“型”
① 記録の原則:事実 → 評価 → 計画(SOAP)
| 要素 | 内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| S(主観) | 利用者・家族の言葉をそのまま引用 | 「『今日は足が重い』と訴え」️ |
| O(客観) | 観察した事実・数値・時刻 | 「歩行速度低下、SpO₂ 96%、食事6割」 |
| A(評価) | SとOからの仮説 | 「疲労+軽度の脱水の可能性」 |
| P(計画) | 次の行動・方針 | 「白湯200ml、午後は外出控えめ。明日も歩行速度を確認」 |
ポイント:
誰が読んでも同じ行動が取れるよう、事実 → 判断 → 次の一手を明確に。
② “悪い記録”を“良い記録”に直す ️
| NG表現 | OK表現 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 「部屋が汚い」 | 「床に洗濯物3点、廊下に紙パック2本」 | 状況を具体的に描写 |
| 「機嫌が悪い」 | 「声量が上がり『帰る』を5回発言」 | 主観を排除し、事実で表す |
| 「いつも通り」 | 「朝食:粥200g、味噌汁半分」 | 定量的に記録 |
判断語を避け、誰が読んでも同じ光景が浮かぶ“再現性のある記録”を意識。
③ 経過記録テンプレ(コピペ推奨)
〈時刻〉8:55 〈出来事〉入浴介助
〈観察〉立ちくらみ×1回(約30秒)
〈対応〉座位休息+白湯100ml
〈結果〉表情改善
〈次回〉入室前の水分声かけ、浴室マット増設検討
3行ルール
1️⃣ 今日起きたこと
2️⃣ なぜ(仮説)
3️⃣ 次回どうする
視認性UPの工夫:
タグ絵文字で定型句を見やすく(例:=入浴/=食事/=口腔ケア)。
④ 引き継ぎメモは“未来志向”で
-
❌ NG:「特になし」「いつも通り」
-
✅ OK:「昼食後に眠気強く、15時の散歩は短めに」「便秘傾向:最終排便8/20」
連絡先も明記
主治医 → 訪問看護 → ケアマネの優先順を統一。
⑤ 監査・指導でつまずくポイントと対策
| よくある問題 | 改善策 |
|---|---|
| 計画と記録のズレ (目標“掃除”なのに内容“会話”ばかり) |
ケア目標を生活目標に翻訳:「来客を迎えたい」など具体化。 |
| 同じ表現のコピペ | 食事量・歩行速度・表情・排泄などの時系列変化を観察。 |
| 個人情報の扱い | 必要最小限の記載+施錠・持ち出しルール徹底。 |
⑥ 家族・多職種に伝わる“短文の型”
「今日は歩行速度が遅めで昼食は6割、白湯で改善。明日は入浴前に水分を先に取ります。」
✨ 1文の構成ポイント
-
数字(定量)
-
比較(変化)
-
次の一手(行動計画)
⑦ 現場ケース:記録の言い換えで転倒予防
-
Before:「ふらつきあり」
-
After:「立ち上がり2回目でふらつき、椅子に手をつかない。夜間トイレ2回」
→ 足元灯+手すり設置を提案し、夜間転倒ゼロを実現。
⑧ 今日から使えるチェックリスト ✅
☐ S/O/A/Pの順に書けたか
☐ 事実と解釈を分けたか(引用と数値)
☐ 次の一手(P)を書いたか
☐ 引き継ぎメモを未来志向で残したか
⑨ ミニワーク(5分)
今日の記録から 判断語を3つ削除 し、
事実表現 に言い換えてみよう。
(例:「元気そう」→「会話時に笑顔・声量一定・歩行安定」)
⑩ まとめ
良い記録は、“賢い現場”の証明。
誰が読んでも同じ対応ができる文章にすることで、
✅ 事故が減り
✅ 情報共有が速くなり
✅ ケアの質が継続的に上がる。
️ 記録は「作業」ではなく、チームの“思考の軌跡”です。
![]()
やまもものよもやま話~🔍 リスクマネジメント~
皆さんこんにちは!
合同会社やまもも、更新担当の中西です。
さて今回は
事故ゼロに近づく“見える化”とチーム運用
① リスクの棚卸し:マトリクスでTop5を決める 🎯
-
評価軸:重大性(S)× 頻度(F)をマトリクスで分類。
例)
- S高 × F高:転倒(夜間トイレ)/誤薬(旧薬混入)
- S高 × F低:火災/誤嚥
- S低 × F高:軽微な打撲/小物紛失 -
方針:
リスクTop5を抽出し、資源を集中投下。
👉 対策例:手すり設置・照明改善・服薬管理仕組み化
② 初動フロー:事実 → 安全 → 連絡 → 記録 → 共有 📣
1️⃣ 事実確認:呼吸・意識・出血の有無をチェックし、周囲の危険を除去。
2️⃣ 安全確保:体位・保温・安静を維持。必要に応じて 119通報。
3️⃣ 連絡:家族 → ケアマネ → 主治医/訪問看護(順序は事業所ルールで統一)。
4️⃣ 記録:事実と推測を分けて記入。
🕒 時刻/場所/状況/対応/結果を具体的に。
5️⃣ 共有:当日中にチーム全体へ報告し、再発防止を迅速に。
③ 再発防止会議の進め方(KPT+5Whys) 💬
-
KPT法
– K(Keep):良かった点
- P(Problem):課題
- T(Try):次の改善策 -
5 Whys(なぜを5回)で真因を掘り下げる
> 例)転倒 → 夜間暗い → 足元灯なし → 設置していない理由は? → 費用/認知の問題 → レンタル提案+家族説明 -
アクション設定
👉 改善策には必ず「期限」と「責任者」をセットで。✅
④ 領域別ミニマム対策 🛠️
| リスク領域 | 最低限の対策ポイント |
|---|---|
| 転倒 | 履物・段差・動線・手すり・夜間照明。歩行スピードと立ち上がり回数を観察。 |
| 誤嚥 | 姿勢・一口量・食形態・食事速度。食後30分は座位保持。 |
| 火災 | IH調理/自動消火装置/感知器設置。外出時は電源チェック表を活用。 |
| 金銭 | レシート貼付・代理受領ルール・財布の定位置化。 |
| 誤薬 💊 | 一包化・ラベル・保管場所固定・旧薬廃棄の徹底。 |
| 個人情報 | 書類の持ち出し最小化。施錠・シュレッダー徹底。 |
⑤ 現場ケース 🌟
-
Kさん(夜間転倒)
👉 足元灯+ポータブルトイレ+ベッド高調整 → 夜間歩行ゼロに。 -
Lさん(誤嚥)
👉 食形態をムース化、“一口ごと嚥下確認”でむせ回数1/4に減少。 -
Mさん(金銭トラブル)
👉 レシート貼付+小額財布導入で家族の不安が解消。
⑥ 監査・指導に強い書類のコツ 📑
-
整合性の確保:
計画書・記録・報告書の表現を統一。 -
ヒヤリハット集計:
月次で件数をグラフ化し、対策実施率も併記。📊 -
研修記録:
参加者/内容/所要時間/振り返りを記載して保存。
⑦ 今日から使えるチェックリスト ✅
☐ Top5リスクを決定し、担当者と対策を明確化したか。
☐ 事故時の初動フローを掲示・周知したか。
☐ ヒヤリハットを月次で集計・KPTで議論したか。
☐ 記録書類の整合性を確認したか。
⑧ まとめ 🛡️
リスクは「なくす」ではなく「管理する」もの。
見える化 × チーム運用で、
在宅の安全と安心を底上げしましょう。
👥 共有・仕組み・継続こそ、事故ゼロへの最短ルートです。
![]()

